在宅医療の現場を救う
オンコール代行の選び方
厚生労働省は高齢者の人口増加に対応するべく、
在宅医療体制を構築するための取り組みを推進。
在宅医療機関が増えていく一方で、
課題となるのが夜間休日のオンコール。
このメディアでは「在宅医療を開業したい」「オンコール体制に限界がある」と感じている方向けに、オンコールを代行するサービスを紹介します。
厚生労働省は高齢者の人口増加に対応するべく、
在宅医療体制を構築するための取り組みを推進。
在宅医療機関が増えていく一方で、
課題となるのが夜間休日のオンコール。
このメディアでは「在宅医療を開業したい」「オンコール体制に限界がある」と感じている方向けに、オンコールを代行するサービスを紹介します。
目次目次

これまでドクター1人で対応していた夜間休日のオンコールを業者に依頼することを「オンコール代行」と言います。
患者さんからの電話に対応してくれるだけでなく、連携しているドクターが患者さんの自宅へ駆けつけ往診してくれるサービスです。
具体的には処方、救急搬送、紹介状作成、HOT導入、オンライン診療、119番連携、地域の救急病院紹介など、患者さんの容体に合わせて適切な医療を提供します。

| 特徴 |
|---|
| 医療訴訟トラブル0件!(※1)高い品質で信頼を担保 |
| 医師+アシスタントの2名で往診代行をすることで、 現場トラブルを未然に防ぐ |
| 看取り患者数5,000名以上(※2)の実績 |
| 地域 |
| 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・兵庫・福岡 |
| 対応時間 |
| 平日:18時~翌9時 土日祝:終日(GW/年末年始含) |

| 特徴 |
|---|
| 3ヵ月無料特典あり(※3) |
| 救急対応にも幅広く対応 |
| 診療連携は自動化・効率化を重視 |
| 地域 |
| 北海道・東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・兵庫・奈良・京都・福岡 |
| 対応時間 |
| 平日:18時~翌6時 土:14時~翌6時 日・祝:終日 |
【このサイトに掲載する会社の選定条件】
2022年12月19日時点、「オンコール代行」「往診代行」とGoogle検索し、公式HPにオンコール代行に関するサービスを提供している16社を掲載。
【2選に掲載する会社の選定条件】
上記会社の中から、以下の条件でそれぞれの会社を選定しています。いずれも公式HP、あるいは公式サービスページを参照しています。
当直連携基盤…在宅医療に特化したオンコール代行サービスを提供しており、支援医療機関数(175診療所)が最も多い(2022年12月19日時点)。
ファストドクター…クリニック向けのオンコール代行サービスを提供しており、全国往診実績(80,341件)が最も多い(2022年12月19日時点)。
※1…問い合わせ後のダウンロード可能な資料に掲載(Relacal編集チーム調べ)
※2…参照元:当直連携基盤公式HP(https://tochoku.com/buddy-on-call)
※3…2024年3月31日23時59分までに東京電力エナジーパートナー(株)へ申し込みし、その後ファストドクターと契約した場合。
参照元:東京電力エナジーパートナー(https://keieisupport.tepco.co.jp/service/fastdoctor)(Relacal編集チーム調べ)
中央社会保険医療協議会より2024年診療報酬改定の答申内容が発表されました。今回、救急往診をはじめとする夜間・休日往診の報酬金額が大幅に減点となりました。(2024年6月1日以降を適用開始)
今回の改定を受け、すでに「みてねコールドクター」は往診のサービス提供の終了を発表しております(※1)ので、
今後も改定を受け、かかりつけ医以外の往診サービスを行っている企業に動きがある可能性がございます。
※1 参照元:みてねコールドクター公式HP(https://calldoctor.jp/news/article/48/)
| 改定後 | 改定前 | |
|---|---|---|
| (1)緊急往診加算 | 325点 | 650点 |
| (2)夜間・休日往診加算 | 405点 | 1,300点 |
| (3)深夜往診加算 | 485点 | 2,300点 |
▼患者の減点対象について
〇減点にならない
・自院または連携先の医療機関の訪問診療を過去60日以内に受けている
・自院の外来に定期的に通院している
・介護老人保健施設や特別養護老人ホームに入居している
〇減点になる
・上記以外
最初にオンコール電話を受電し、病院への連絡や救急搬送手配などを含めた適切な判断・対応を行います。特定のクリニック名で対応する事も可能です。
オンコール代行サービス会社に所属する医師・看護師・救急救命士などの有資格者が、患者への適切な対応を指示します。
主治医に代わり、オンコール代行サービスに所属する医師が患者を往診します。必要に応じ医療行為も行います。
介護施設のスタッフに向け、医師監修の対応マニュアルを作成・提供します。マニュアルに沿った動きにより、現場業務が効率化します。
介護施設のスタッフに向け、救急対応研修を実施します。あらゆるスタッフに救急対応法を習熟させることで、サービスの質の向上を図ります。
請求書や領収書の発行、訪問看護指示書の発想、電子カルテへの入力など、各種バックオフィス業務を代行します。

通常業務に加え、オンコール業務がある場合はオンコール対応後、そのまま出勤をすることも珍しくありません。
時に、この生活リズムが数日続くこともあります。オンコール業務を依頼することにより、精神的・肉体的な負担が激減します。
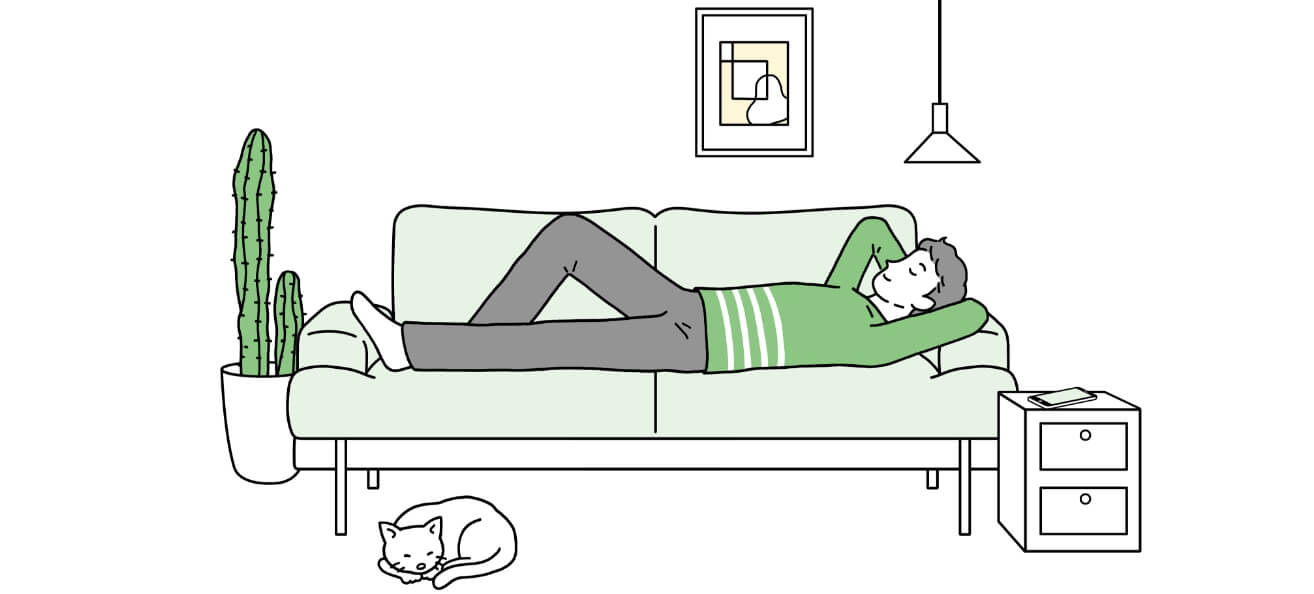
24時間365日対応を要する在宅医療。クリニックによってはドクター一人で何人もの患者さんを診ていることから、いつでも電話がつながるようにPHSや携帯が手放せず、プレッシャーを感じているドクターもいます。
オンコール業務を任せられるということは、他の業務に専念できたり、十分な休息をとったりすることができます。

医療提供のための、夜間休日の人員体制、オンコールの往診車の手配についてもコストがかかります。
オンコール体制を維持するためにかかるコストとオンコール代行にかかるコストを比較すると、コストダウンに繋がることもあります。

求人を探す基準の一つとして、「オンコールなし」である条件を挙げる、医師や看護師 もいるようです。
オンコールの負担がない分、医師や看護師の応募が増え、採用がしやすくなるケ―スもあります。
オンコール代行会社と一口にいっても、料金、対応エリア・時間など、会社によりサービスが異なります。また、サービスの違いを理解すると自院に合ったオンコール代行サービスを導入することができます。
救急外来(往診)の診療も定期の訪問診療も「医師の診察」という機能では同じです。
下記に違いをまとめていますので、オンコール代行会社選びの参考にしてください。
| 在宅医療の救急往診 | 一般患者の救急往診 | |
|---|---|---|
 |
 |
|
| 特徴 | 診療方針・終末期の希望を踏まえた全人的判断 | 症状に応じた的確な医療判断 |
| 目的 | 納得・最期の伴走 | 治療・回復 |
| 登場人物 | 当直医師・患者・家族・主治医・地域事業所・設備職員 | 当直医師・患者 |
| カルテ連携 | 必要 | 不要 |
多くのクリニックで利用されている導入実績があれば、充分なノウハウやマニュアルの構築がされていると考えて良いでしょう。
導入実績、往診実績や提供医療機関数に注目すると、会社の信頼度をはかるうえで参考になります。
▼横スクロールできます▼
| 看取り実績 | カルテ連携の有無 | 対応エリア | 往診対応時間 | |
|---|---|---|---|---|
|
バディ往診 (株)当直連携基盤 |
看取り患者対応実績:5,000人以上 | 切れ目のない 在宅医療のため カルテ連携を重視 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 愛知 大阪 兵庫 福岡 |
平日:18時~翌9時 土日祝:終日 (GW/年末年始含) |
| ファストドクター | 看取り患者対応実績:- | 緊急往診など 速やかな対応の為 カルテ連携は不要 |
北海道 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 大阪 兵庫 奈良 京都 福岡 |
平日:18時~翌6時 土:14時~翌6時 日・祝:終日 |
▼横スクロールできます▼
| 往診後の対応 | サービスの品質 | |
|---|---|---|
|
バディ往診 (株)当直連携基盤 |
カルテとより細かい情報の バディレポートを提出 患者の情緒的な報告や ご家族とのやり取りまで きめ細やかな報告 |
当直医と一緒に メディカルバディ(診療アシスタント)が同行 診療アシスタントは 数か月の在宅医療専門研修・OJTの 経験を叩き込まれた 在宅医療のスペシャリスト |
| ファストドクター | 独自のクラウドシステムにより オンライン上で完結 往診後翌朝までには進捗の確認が可能 |
救急医・内科医・小児科医・整形外科医など 対応できる診察が多種多様 担当医師は参画医療機関や 大学病院に所属 |
医師と家族という第三者を挟まない空間になるから、医療訴訟などのトラブルが発生をしないよう心掛けてほしい

5,000名以上の在宅医療でも医療訴訟などのトラブルは0件。家族とのやり取りなどを把握していないと発生し、後々「どうしてその対応を行ったのか」が問題になります。 当直医師に代行するメディカルバディ(アシスタント)が同行するので第三者視点からの報告によりトラブルに発展しません。
色んな現場を知っていたり、ノウハウが蓄積していた方が安心できるので、実績数があったほうが良いかな

色んな現場を知っていたり、ノウハウが蓄積していた方が安心できるので、実績数があったほうが良いかな
所属している医師が1,250名以上、年間相談件数80,000件の実績があります。一日あたり70台の往診チームが稼働しており、現場を知っている医師も増えるため、毎日ノウハウがたまっていきます。そうしたノウハウの蓄積も医師の方々に安心していただける要素の一つです。
かかりつけ医としては、現場でどのような対応をしたのか、患者さんの様子がどうだったのか気になるので詳細に報告が欲しいな。

当直医師に同行したメディカルバディ(アシスタント)が【どのような対応をしたのか】といった部分や【実際のご家族の反応はどうだったのか】などを事細かにまとめた「バディレポート」をカルテとは別に報告します。その後の患者のやり取りや声がけに繋がる情報をお渡しします。
自院の先生以外の当直医師にお願いをするので、実際にどんな対応になったのか瞬時に把握していたい。

自院の先生以外の当直医師にお願いをするので、実際にどんな対応になったのか瞬時に把握していたい。
独自のクラウドシステムである「クリニックポータル」を導入いただきます。診療支援業務をスムーズに進行させるため、依頼~申し送り~報告をすべてワントップで対応。そのため、時間がかかっていた報告も、オンラインですぐに進捗を確認することが可能です。
いままで地域のみなさんと地道に築き上げた信頼関係があります。しっかり患者さんひとりひとりに合わせた対応をするため、カルテ連携はしっかりしていないと困ります!

在宅医療に特化している当直連携基盤では「在宅患者への臨時対応は主治医の診療と切れ目無く繋がった医療を提供」を主軸に置いています。
細かなカルテ連携により、患者さんやご家族に主治医と当直医の「医療の差」を感じさせない対応をこころがけています。
緊急の往診の場合など、
カルテを共有している時間が惜しいです。
こちらが細かな指定をしなくても対応してくれる会社がいいな。

緊急の往診の場合など、
カルテを共有している時間が惜しいです。
こちらが細かな指定をしなくても対応してくれる会社がいいな。
どんな医院のオンコール代行にも速やかに対応するため、ファストドクターでは「カルテ連携は不要」と言い切っています。
もちろん、個人情報の確認はしますが、最低限の情報で臨機応変に対応しますという企業側の自信の表れでもありますね。
人生の最期を看取ってほしいと言っている患者さんが多いです。万が一、看取る際にも慌てることなく対応してくれる医療チームがいいな。

終末期の患者さんが生き生きと暮らせるように、医師・診療アシスタント・家族・訪問看護師・ケアマネ・施設職員がワンチームで対応。看取り対応実績はなんと3,000名以上で日本一(※2022年11月1日時点)。
基本的には在宅医療に特化していますが一般的な診療にも応じてくれます。
コロナの自宅療養者診療や外来患者の急診など、様々なケースがあります。要望に合わせて的確な医療判断をしてくれるとありがたい!

コロナの自宅療養者診療や外来患者の急診など、様々なケースがあります。要望に合わせて的確な医療判断をしてくれるとありがたい!
新型コロナウイルスの抗原検査や急なケガや病気で動けなくなってしまった外来患者の診察やオンライン診療、緊急判定(トリアージ)、119番連携、など、様々な診療に対応しています。
かかりつけ医のいない慢性疾患の患者さんを紹介することもできるので、新たな接点を持つことができます。
基本的には、ご家族と決めた当院の対応方針に従ってほしい。やむを得ず違う対応をする場合は、その判断に至った背景や、そのときのご家族の心境なども教えてもらえると助かります!

在宅医療の往診代行で重要なのは、主治医と当直の対応基準を合わせること。多くの在宅医療機関を支えてきた当直連携基盤は方針として主治医に従うよう徹底。
また、当直医師からの報告だけでなく診療アシスタントによる第三者目線での報告も充実しており、患者さんとご家族のケアを第一に対応してくれます。
緊急の場合も多いため、適切な処置をその場で素早く判断して対応ほしい。患者さんの重症度を現場で見極めて、治療の優先度を適切に判断してほしいです。
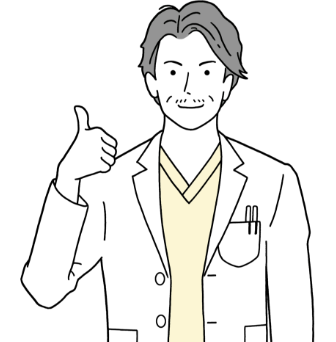
緊急の場合も多いため、適切な処置をその場で素早く判断して対応ほしい。患者さんの重症度を現場で見極めて、治療の優先度を適切に判断してほしいです。
患者さんの容態の重症度に基づき、ファストドクターでは症状に応じて、往診医師の判断で適切な医療を施せるようにしています。
緊急度判定プロトコール(総務省消防庁準拠)をもとに、翌日以降の診療や緊急搬送といった適切なトリアージによって処置を決めています。
もちろん腕の良い医師を希望します!ただ、割り切ってうちの対応方針に従ってくれる潔い人が良いなと思っています。在宅医療に理解のある人がいてくれると安心です。

かならず在宅医療の経験のあるスタッフが往診同行を行うのが当直連携基盤の強み。
医院の対応方針に準拠し、徹底して対応してくれるのも、患者さんやご家族と主治医の関係性が重視される在宅医療への理解が深い当直連携基盤ならでは。
そりゃ腕が良く経験の豊富な医師がたくさん登録されていることが大事です。いざという時に素早くしっかりカバーしてほしいので。教育制度もしっかりしていてほしいですね。

そりゃ腕が良く経験の豊富な医師がたくさん登録されていることが大事です。いざという時に素早くしっかりカバーしてほしいので。教育制度もしっかりしていてほしいですね。
所属医師が1.620名(※2022年11月1日時点)というファストドクター。
専門分野に精通した医師を多く抱えています。在宅医療の往診の経験がない医師であっても、研修を実施することで往診代行を可能に。教育制度も整っています。
知名度というより、多くの医院に取り入れられているかどうかは気にしますね。宣伝上手よりも、口コミや紹介でお客が途切れない「知る人ぞ知る老舗」が信頼できる!

当直連携基盤は往診代行サービスのパイオニア的存在。2018年のスタート以降、181以上の医療機関を支援(2022年11月1日時点)。
3万人超の在宅患者の臨時対応を、地域毎に配置した在宅医療専門当直チームが対応。契約継続率は96%に達しており、満足度の高さがうかがえます(2022年11月1日時点)。
知名度はもちろん、メディアで取り上げられていて一般の方にも知られていると尚ありがたい。患者さんの安心にもつながるから。うちの理事長に説明するときにも話が早いし!

知名度はもちろん、メディアで取り上げられていて一般の方にも知られていると尚ありがたい。患者さんの安心にもつながるから。うちの理事長に説明するときにも話が早いし!
もともと一般向けの夜間の往診からスタートしたサービス。
テレビや新聞といった各方面のメディアに露出しており、医療関係者以外にも知名度があります。
東京都や大阪府など、自治体との連携実績もあるため、信頼度が高いですね。
サービス内容


医師が変わっても患者さんが安心している
30年近く在宅医療に携わっており、多い時には160人を超える患者さんを、24時間365日ほぼ自分ひとりで診ていました。
40歳を過ぎるころには身体に限界を感じ、「この仕事をしている限り50歳までは生きられないだろう」と思うようになりました。
そんな状況を見かねたスタッフが当直連携基盤のオンコール代行サービスを見つけてくれて、導入することに。
最初のころは「本当に大丈夫かな?」と思っていましたが、当番の先生がしっかり診てくれることがわかってきて、患者さんも安心してくれている様子もよくわかってきました。

診療アシスタントの報告内容が充実!
実際に診察をうけた患者さんたちからも当直医師の対応について良かったと言って頂けており、日勤帯との違和感がないスムーズな当直対応をしてくれていると感じています。
加えて安心材料は2点ありまして、1つは当直医師がカルテ情報に基づいたアセスメントを行ってくれている点です。
2つ目は診療アシスタントの報告記載が充実している点です。
医師とは違う目線で、診察の状況や処置内容、使用物品、診察の同席者などを事細かに記載されています。
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県 ※コールセンターは全国対応 |
|---|---|
| 登録医師、看護師 | 当直医師628名(男性:482人 女性:146人) 社員(診療アシスタント)49名 (男性:24人 女性:25人) |
| 支援医療機関 | 175診療所 6病院(2022年8月1日時点) |
| サービス提供時間 | 平日夜間:18時〜翌9時 土日祝:終日(GW・年末年始含) |
| 会社名 | 株式会社当直連携基盤 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本石町3-2-3 日本橋オリーブビル9階 |
| 電話番号 | 03-6666-9277 |
| 公式HPのURL | https://www.tochoku.com/ |
※1…問い合わせ後のダウンロード可能な資料に掲載(Relacal編集チーム調べ)
※2…在宅医療専門のオンコール代行会社の中で最も多く往診対応(13,740万人、2019年4月~2022年7月の期間)をしている。参照元:当直連携基盤公式HP(https://www.tochoku.com/)
サービス内容


対応や情報共有が丁寧だから、安心です
(前略)ファストドクターは診療体制が明確で、フットワークが軽く、患者さまをお待たせしないところが提携の決め手となりました。
実際に、患者さまにとても丁寧に対応くださっている印象で、カルテに詳細に記入しフィードバックしてくれるので、翌日には状況がわかり安心です。

「患者さまにできること」を増やすために
もともと在宅医療の体制確保の一環で、多職種と連携し組織化する取り組みを行っており、さらにファストドクターと連携することで医療提供の質や持続可能性の向上につなげています。
(中略)日頃から連携を意識していれば、患者さまが夜間・休日に受診しても「価値のある医療」を提供できると思います。
| 対応エリア | 提携医療機関より半径16キロ圏内が対応エリアです。 1都1道2府7県にて連携医療機関があります。 北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、福岡県 |
|---|---|
| 登録医師、看護師 | 医師:1,650名以上(常勤+非常勤) 看護師:該当する情報を発見できませんでした |
| 支援医療機関 | 参画医療機関:23施設+他複数医療機関と連携 |
| サービス提供時間 | [平日] 18:00~翌6:00 [土]14:00〜翌6:00 [日・祝] 6:00~翌6:00(24時間対応) オンライン診療 [月〜日・祝]24時間 |
| 会社名 | ファストドクター株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区芝4丁目5-10 EDGE芝四丁目ビル3F |
| 電話番号 | 03-6387-3499 |
| 公式HPのURL | https://fastdoctor.jp/ |
※1…オンコール代行会社の中で最も多く往診実績(80,341万人、2022年12月時点)がある。参照元:ファストドクター公式HP(https://oncall.fastdoctor.jp/)
在宅医療に特化したオンコール代行・夜間休日の往診サービスを提供。診療アシスタントと呼ばれる第三者の目線から当直医師の対応をジャッジします。
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本石町3-2-3 日本橋オリーブビル9階 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6666-9277 |
| 公式HPのURL | https://www.tochoku.com/ |
地域包括ケアサービスのバックアップについて強みのある会社。24時間365日対応の在宅医療提供をサポートします。
| 所在地 | 東京都港区新橋4-31-3第3明和ビル |
|---|---|
| 電話番号 | 該当する情報を発見できませんでした。 |
| 公式HPのURL | https://oncall-japan.com/ |
全国の医療機関から構成されている時間外救急の総合窓口を謳っており、患者さんの症状に応じて適切な医療を選択します。
| 所在地 | 東京都港区芝4丁目5-10 Edge芝四丁目ビル3F |
|---|---|
| 電話番号 | 該当する情報を発見できませんでした。 |
| 公式HPのURL | https://oncall.fastdoctor.jp/ |
夜間休日のオンコール代行、平⽇の診療時間帯における、緊急往診の代⾏にも対応。基本料金はなく、患者1名単位ごとの料金体制。
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘6-82 |
|---|---|
| 電話番号 | 0942-82-4400 |
| 公式HPのURL | https://tsutsumiclinic.net/2022/09/05/つつみクリニックではオンコール代行業務を行っ/ |
対象は小児~高齢者を対象に薬の処方・受け取りや、各種診断書の作成もその場で対応可能です。365日夜間と休日に医師が派遣されます。
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-10-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6381-7511 |
| 公式HPのURL | https://piq.jp/lp/ |
在宅支援診療所、外来専門診療所とそれぞれの形態によって、サービスの種類を用意しています。往診のみの代行ができる”夜間出勤サポート”も有り。
| 所在地 | 東京都千代田区一番町6番地 一番町SQUARE 5階 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3221-7012 |
| 公式HPのURL | https://medical-de-sign.co.jp/business/medical_support.html |
残りの10社も見る閉じる
オンコールとは、患者さんや利用者の急変時に、医師、看護師、介護士などの医療・介護従事者が、いつでも対応できるよう待機することをいいます。
オンコールにおける課題と解決策としての代行サービスについて紹介します。
オンコール代行サービスの導入は、在宅医療を提供している医療機関にとってさまざまなメリットがあります。例えば医師やスタッフの負担の軽減や離職防止、在宅医療にかかる人件費の削減などが期待できるといえるでしょう。こちらの記事では、期待できるメリットと、代行サービスに依頼できる業務についてまとめています。
医療福祉施設で、オンコール代行を利用している会社において、離職率低下という成果が出ています。
オンコール代行は、各医療福祉施設において、具体的にどのような役割を果たし、活用されているのでしょうか。
積極的に在宅医療へ取り組む医療機関にとっては、オンコールによる急患対応は必須です。
オンコール代行を利用することで医師の精神的・身体的負担の軽減が期待できます。
外注の医師との連携はカルテを通してのコミュニケーションを行うことがカギになります。
主治医と当直医がカルテを連携することによって、患者さんの困った時に、早急な対応ができるでしょう。
やりがいがある一方、大変さを感じる医師・看護師・職員も少なくありません。
オンコール業務を外注することで、日中の業務に集中できたり、オンコール業務がないことで職場の定着率があがったりするなどのメリットが生まれることがわかりました。
実際にオンコール代行を導入された3つ事例を紹介します。どんな経緯で導入に踏み切ったのか、クリニックや施設が抱える オンコールの課題を見ていきましょう。
実際オンコールを導入する場合、契約~サービス開始まで、2か月前後かかるケースが一般的です。
ここではオンコール導入までの流れについて、ご紹介します。
オンコール代行を検討する際のFAQをまとめました。看取りの対応について、往診結果の共有、当直医とのカルテ連携といった気になる疑問を解決します。
オンコール代行サービスと一口にいっても、導入する際の選び方について、ポイントを押さえておく必要があります。
クリニックや施設の規模、料金、対応エリアや時間等の比較をしましょう。
看護師の数が十分で問題なく回せているような場合は、必ずしもオンコール代行が必要とはいえません。
どのような施設がオンコール代行の導入について前向きに検討するべきなのかなどについて解説します。
オンコール代行の料金相場はプランにより変わります。従量課金制ならコール数によって、通話無制限プランであれば入所者数によって変わるためです。オンコール代行のプランごとの料金相場について解説します。
オンコール代行は、導入にコストがかかることや外部委託に不安を感じる声があがりやすいことがデメリットです。しかし、昨今の人手不足の状況を考えれば、看護師を新規採用するよりも、コストや労力の削減効果が期待できます。
オンコール代行業者の中には、オンコール代行後にレポートやカルテ作成を行い、医療機関に共有してくれるところがあります。レポートやカルテ作成まで代行してくれれば、職員の負担を軽減し、医療サービスに集中できるようになるでしょう。
オンコール代行の中には、患者さんとビデオ通話により診療を行うものもあります。ビデオ通話ができると患者さんの容態をより正確に把握でき、ボディランゲージによってコミュニケーションが取りやすいメリットがあります。
オンコール代行を導入すると、看護体制加算を取得しやすくなります。なぜなら看護体制加算の算定要件に「24時間連絡ができる体制が整っていること」があるためです。看護体制加算の算定を目指すには、オンコール代行が便利でしょう。
特養でオンコール代行を導入すると、従業員の負担軽減はもとより、求人への応募数も増える傾向があります。オンコール代行の導入事例を確認すれば、特養での導入にどのようなメリットがあるのかおわかりいただけるでしょう。
オンコール実態について調査した結果を見ると、待機時間中は勤務時間とみなされないこと、電話対応は勤務とされないことがほとんどです。スタッフへの労働時間外の負担が大きいことが推察され、各医療機関・介護施設にて対策が必要です。
オンコール勤務中は残業時間に当たるのでしょうか。一般的に「自宅など一定の場所から離れられない」「病院から連絡を受けて病院に向かわなかった場合不利益な処分を受けるとされている」など客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下にあるといえる場合は、オンコール待機中も残業時間として見なされる可能性があると考えられます。
オンコール業務は、働くスタッフへの負担が非常に大きい業務といえるでしょう。そのため、スタッフの精神的・身体的な負担をどうすれば軽減できるかを考え、対策を行っていくことが大切です。こちらの記事では、人材確保やマニュアル整備、働きやすい環境の整備、オンコール代行サービスの導入など様々な対策をご紹介しています。
オンコール対応は医師や看護師など医療従事者にとって負担が大きいため、少しでも負担軽減をする必要があります。♯8000子ども医療電話相談事業や#7119救急安心センター事業などは、患者側の精神的な負担軽減になるだけではなく、医療スタッフの負担軽減にもつながります。ここでは、緊急対応の負担軽減に役立てたい自治体窓口についてご紹介しています。
オンコール業務は、医療スタッフへの負担が大きい業務の1つです。しかし、オンコール明けの取り扱いは、実際に呼び出されて働いた場合に限りますが、翌日勤務を代休とするかどうかは、医療機関側の裁量で決められます。代休を与えなかったとしても、出勤時刻を遅らせるなどの配慮が必要です。ここでは、オンコール時間における代休・手当の取り扱いをご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
長時間労働や慢性的な人手不足など、看護師が離職を考える原因にはさまざまなものがあります。対して、離職率を下げるための取り組みとしては、福利厚生の充実や働き方改革の推進、オンコール代行の導入などの方法が考えられます。オンコール対応がなくなることで、現場の負担を軽減できるとともに求人への応募が増える可能性もあります。
2024年4月から「医師の働き方改革」が始まるように、現在は医院やクリニックにおいて働き方改革が進められている状況となっています。そこで、働き方改革は医院やクリニックにどのような影響を与えるのかといった点についてまとめています。また、長時間勤務の問題を解消するための一つの方法として、オンコール代行の導入についても説明しています。